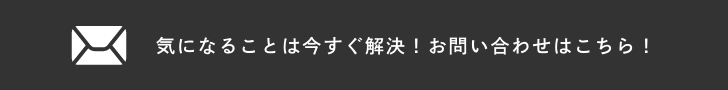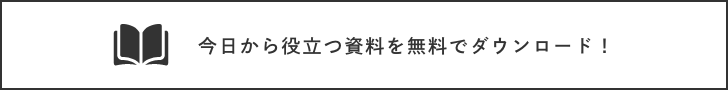INDEX
1.はじめに:なぜ今「顧客体験(CX)」がマーケティングの鍵なのか
現代では、製品やサービスそのものの機能・価格だけでは、顧客の心を掴みにくくなっています。顧客は購入前の情報収集から、Webサイト・SNS・実店舗での接点、購入後のフォローまで、「どんな体験をしたか」を重視するようになっており、いわゆる「顧客体験(CX)」がマーケティング戦略の中心に据えられています。 
特に、オンライン・オフラインを問わず顧客接点が多様化・複雑化したこと、また機能や品質といった“合理的価値”がコモディティ化してきたことが、CX重視の背景にあります。 
中小企業・地方ブランドにとっても、この潮流はむしろチャンスです。大手と同じ土俵で「機能・価格」で勝負することが難しいからこそ、「体験」「対話」「関係性」といった価値を通じてマーケティングを設計できれば、ブランドの差別化・ファン化・持続的な収益モデルにつながる可能性があります。
2.現状の課題:分断されたWeb・SNS・実店舗がブランドを弱めている理由
現代の顧客接点は、Webサイト、SNS、実店舗といった多様なチャネルに広がっています。一方で、これらを統合せず個別に運用していると、ブランドが発信するメッセージがバラバラになり、顧客にとって「体験の連続性」が失われてしまうという課題があります。
例えば、Webサイトでは商品仕様や価格の情報提供に終始し、SNSではキャンペーン投稿だけが独立して行われ、実店舗では接客・販売のみが完結する――こうしたチャネルごとの“分断”状態では、顧客はブランドを通じて一貫した「体験」を得られません。実際、チャネルが分断されていると、統一されたブランドメッセージを保つことが困難になるという調査があります。
さらに、チャネル間の齟齬は顧客の混乱を招き、ブランドへの信頼を低下させるリスクがあります。多くのマーケターが「複数チャネルを実行しているが、整合性を保つことが最も難しい」と回答しています。
特に中小企業・地方ブランドにおいては、限られた人的・予算的リソースの中で、「Webサイトを作って終わり」「SNSを投稿して終わり」「実店舗で販売して終わり」という運用になりがちです。その結果、各接点が個別最適化される一方で“顧客にとっての体験の流れ”が設計されず、ブランドの印象が表面的・断片的になってしまいます。
そしてこの分断は、せっかく集めた顧客接点をファン化・リピート化へつなげることを難しくします。顧客は「このブランドは私にどう関係してくれるのか」「次にどんな体験があるのか」という期待を持つものですが、接点がバラバラではその期待を裏切る可能性があります。
次節では、こうした分断を解消し、「体験を統一する」ための具体的な4ステップをご紹介します。

3.成功の骨格:ブランド体験を統一するための4つのステップ
ブランド体験を統一し、チャネルをまたいで顧客に一貫した印象を与えるためには、以下の4つのステップを順に実行することが効果的です。
ステップ1:理想顧客(ペルソナ)/ブランドストーリーを明確にする
まずは「誰に」「何を」「どんな価値(体験)を与えるか」を整理します。顧客の行動・心理・価値観を描いたペルソナを設定し、それに基づいて自社ブランドのストーリー=「このブランドはどんな存在なのか」「顧客とどんな関係を築きたいか」を明文化します。これによって、Web・SNS・実店舗を通じた体験設計の軸がブレずに定まります。
ステップ2:Web・SNS・実店舗で共通する「ワンメッセージ」と「トーン&マナー」を設計
ペルソナ/ブランドストーリーが固まったら、すべてのチャネルで使う「ワンメッセージ(核となる言葉)」「トーン&マナー(語り口・デザイン・接客の雰囲気)」を設計します。例えば、「地域とともに成長する手しごとブランド」というメッセージを基点に、Webサイトはナチュラルな写真と穏やかな語り口、SNSでは顧客の暮らしに寄り添う投稿実例、実店舗では地域の素材・地域スタッフを活かした接客という“雰囲気の統一”を図ります。これにより、顧客はどこで接触しても「このブランドらしさ」を感じられます。
ステップ3:顧客接点ごとに“体験設計”を入れる(例:Web→SNS→店舗の動線設計)
次に、各チャネルをただ運営するだけでなく、「顧客がブランドと出会ってから、どのように歩むか」の動線を設計します。例として、Webサイトではブランドストーリーを伝えて関心を引き、SNSでユーザーの日常にブランドがどう入り込むかを見せ、実店舗ではその体験を実際に触れて感じられる仕掛けを用意。さらに、来店後にフォローアップSNS投稿や会員メールで「次回体験」を提示、という流れがあると、体験が“連続”します。こうしてチャネルをまたぐ体験設計は、顧客の満足度とブランド接点の価値を高めることができます。
ステップ4:KPIとフィードバックを回す仕組みを作る(数値+定性)
最後に、体験設計の成果を測定し、改善を回していくための仕組みを整えます。数値面では「リピート率」「顧客生涯価値(LTV)」「NPS(推奨意向)」などをモニタリングし、定性面では「SNSでのブランド言及」「店舗での接客フィードバック」などを収集します。これらを元に「どの接点の体験が弱いか」「どのメッセージが伝わっていないか」を可視化し、改善サイクルを回すことが、ブランド体験を維持・向上させるために不可欠です。
また、体験設計は一度作って終わりではなく、顧客期待・チャネル環境・技術変化に応じてアップデートを続けるべきです。

4.実践事例:地方の中小企業が体験設計で変わった3つのケース
ブランド体験をしっかり設計し、Web・SNS・実店舗をつなげたことで成果を出した、地方/中小企業ならではの事例を3つご紹介します(仮想事例をベースに構成していますが、実際に類似の取り組みが各地で成功しています)。
製造業A社のWeb改修+SNS発信で体験を変えた例
北海道内で伝統製法を守る木工家具メーカーA社は、「機能・品質勝負」だけで競うには限界を感じていました。そこで、まずWebサイトをブランドストーリー型に全面改修。「この家具は、地元の木材と職人の技で、あなたの暮らしに美しい時間をもたらします」というメッセージを前面に出し、SNSでは“職人の手元”や“素材が家具になる過程”を動画・投稿で定期発信しました。さらに、実店舗では来店者に“小さな木片”を手に触れてもらい、「材から家具へ」のストーリーを体感できるブースを設置。こうした流れで「知る→興味を持つ→触れて買う」という体験の動線が整いました。その結果、Webサイト経由の問い合わせ数が前年比+40%、リピート購入の比率も明確に改善しました。
地域店舗B社の実店舗+SNS+会員プログラムを統合した例
地方の雑貨・カフェを運営するB社(地方都市中心)は、実店舗での購買が中心でしたが、SNS活用や会員制度までは手が回っていませんでした。そこで、SNS(Instagram)で“商品背景ストーリー”を投稿し、フォローした来店者に実店舗で「SNS投稿画面を提示」で限定ドリンクを提供する仕組みを導入。さらに、店舗で会員登録した顧客には専用のオンライン限定コンテンツ(工房見学動画・職人インタビュー)をメール配信。こうして「オンラインで興味を引き、実店舗で体験し、会員で継続フォロー」を設計しました。結果として、SNSフォロワー数が2倍になり、来店率及び会員登録率も増加。顧客滞留とクロスチャネル体験がブランドへの愛着を高める要因となりました。
サービス業C社のオンライン体験設計+フォロー体制でリピート増加した例
地方の宿泊サービスC社は、過去「予約→宿泊→お礼メール」で終わっていました。そこで、Web予約の段階で「滞在前に選べる体験メニュー(地元ガイド付き散策/夜の焚き火トーク)」をWeb上で見せ、滞在中は専用SNSのハッシュタグで顧客写真を集めてリアルタイムで宿泊者専用ストーリーに発信。宿泊後には「次回限定クーポン+アンケート動画」で“次回も体験を続けよう”という動線を設計しました。こうした取り組みにより、リピート率が明確に上がり、口コミ評価も改善。顧客が「また来たい」と思える体験設計がブランド価値を高めました。
5.依頼を検討する際のポイント:なぜ“伴走型マーケティング会社”が必要か
自社のマーケティングを内製だけで完結させようとすると、戦略立案はできても“継続的な実行・改善”が停滞してしまうケースが少なくありません。そこで、“伴走型のマーケティング支援会社”に依頼する意義があります。「伴走型」とは、単に戦略を提示するだけでなく、実行フェーズからモニタリング・改善までを長期視点で一緒に進める支援形態です。
ここでは、伴走型を選ぶ際のポイントを3つに整理します。
内部だけでやろうとすると陥りがちな落とし穴
まず、社内でマーケティングを完結させようとすると、どうしても「やるべきこと」が散漫になりがちです。担当者が毎日の運用に追われ、戦略を再考・改善する余裕がなくなったり、チャネルごとに担当が分かれ“分断”された動線のまま継続されてしまったりします。その結果、体験設計(CX設計)で挙げたような「Web・SNS・実店舗の統一体験」が崩れてしまうのです。
外部に依頼する際の選び方:戦略+デザイン+運用がセットであるかどうか
外部パートナーを選ぶ際には、ここが重要なチェックポイントです。
• 戦略設計ができるか:単なる広告運用代行ではなく、「ペルソナ設定」「ブランドストーリー」「体験設計」まで踏み込んでいるか。
• デザイン・クリエイティブがあるか:Web・SNS・実店舗で表現するトーン&マナーが整っているか。
• 運用・改善支援まで伴走してくれるか:KPI設定・モニタリング・レポート・改善提案など、実行と改善のサイクルを回せるか。
これらがワンストップで担えていれば、チャネル横断の体験設計をトータルで任せやすくなります。
依頼時に押さえるべき3つの契約・成果確認ポイント
最後に、実際に契約を交わす際に押さえておきたいポイントを3つご紹介します。
1. 成果指標(KPI)と評価方法の明示 — 例えば「リピート率○%」「Web問い合わせ数○%増」など、数値化できる目標が設定されているか。
2. 役割分担の明確化 — 自社が何を担い、支援会社が何を担うのかを明確にし、「ただ丸投げ」にならない構造にすること。
3. 定期レビューと改善プロセスの設計 — 月次/四半期ごとのレビュー、改善提案の機会が盛り込まれているか。体験設計は一度で終わるものではなく、顧客やチャネルの変化に応じてアップデートが不可欠です。
以上のような観点を持ってパートナー選定と契約設計を進めることで、ただ「依頼したら終わり」ではなく、ブランドを一緒に育てる「伴走型」関係を築くことが可能になります。次節では、読者自身が「今すぐできる小さなアクション」と、次のステップについてご案内します。
6.おわりに:今すぐできる小さなアクション3つ+次のステップご案内
ブランドとして「体験設計(CX)」を軸に据えるためには、大規模なプロジェクトを待つ必要はありません。まずは今すぐできる“小さなアクション”を3つ取り入れ、次のステップへの土台を築きましょう。
アクション1:Webサイトのファーストビューを「ブランドストーリー」に変える
多くのWebサイトは商品の仕様や特徴を並べて終わってしまっていますが、理想顧客(ペルソナ)が共感するブランドストーリーをファーストビューに据えるだけでも、“このブランドから体験が始まる”という印象を強められます。たとえば「地域の素材で、あなたの暮らしに馴染む家具をつくる」というメッセージを、キャッチコピー+ビジュアルで提示するようにしましょう。
アクション2:SNS投稿を“顧客の日常”にフォーカスする
SNS発信も、単なる「商品紹介」ではなく、「このブランドが顧客のどんな日常に寄り添えるか」を切り口にした投稿に切り替えましょう。例えば顧客がその商品を使った時間、感じた気持ち、あるいはその利用シーンを撮った写真と小さなストーリーを添えることで、体験のイメージが生まれやすくなります。
アクション3:実店舗受付や接客のトーク設計を“顧客の理想体験”に合わせる
実店舗を持つ場合には、「ただ商品を売る」のではなく、「このブランドとの関係が始まる場」という位置づけに接客を変えるのがおすすめです。来店時の会話や案内の言葉、店内の導線・サイン表示・照明・音楽など、さまざまな要素に“顧客が期待する体験”を意識してみましょう。たとえば「初めて来店されたお客様へ」「このブランドを知っていた方へ」といった来店のきっかけに応じた声かけを用意するだけでも、印象が変わります。
――
これら3つのアクションを小さく実施しながら、次のステップとして「チャネル横断の体験設計ロードマップ整備」「KPI・フィードバック回収体制の構築」へと進むことをおすすめします。そして、それらを実行していく際には、戦略立案・設計・運用・改善を一緒に進められる“伴走型マーケティングパートナー”としてのご相談もぜひご検討ください。
ご興味・ご相談がありましたら、無料相談窓口/資料ダウンロードをご案内しております。お気軽にお問い合わせください。

商藝舎の視点
地域の飲食業を運営するお客様では、SNSと店舗の雰囲気がうまく噛み合わず、伝わり方に差が出ていました。そこで一緒にブランドの“理想の一日”を描き、Web・SNS・店舗で共通するストーリーを再設計。『お客様が来てくれる理由が変わった』と喜んでいただけたのが印象的でした。