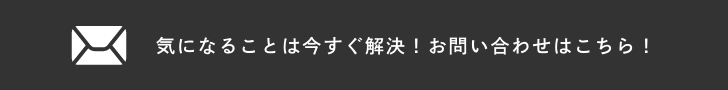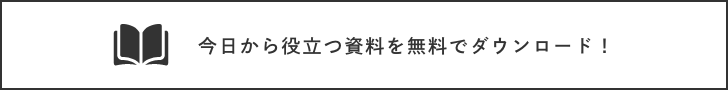INDEX
1 はじめに:数字を見せることは、候補者の時間を尊重すること
「人が辞めにくい会社です」と言葉で言うのは簡単ですが、応募者が知りたいのは根拠です。定着率や平均勤続年数、育休復帰など、離職や継続に関わる指標を“出せるかどうか”。ここに、採用コミュニケーションの質が表れます。完璧な数字を並べる必要はありません。むしろ大事なのは、定義を明かし、更新時期を明示し、文脈を添えることです。隠さない姿勢は、候補者の意思決定コストを下げ、結果として「選ばれる側」にまわる近道になります。

2 なぜ“隠さない”が採用力に効くのか
予測可能性が不安を小さくする
入社後の見通しが持てない不安は、辞退の大きな要因です。定着に関する基礎情報が最初から見えていれば、候補者は「入社後のギャップ」を自分で評価できます。
期待値調整がミスマッチを減らす
数字は魔法ではありませんが、期待のベースラインを合わせます。過度な期待も過度な警戒も薄れ、選考中のやり取りが落ち着きます。
誠実さのシグナルになる
良い面だけを切り取らない企業は、入社後の説明も誠実だろうと解釈されます。心理的安全性の初期印象づくりに、透明性は直結します。
改善サイクルが回り出す
公開は社内への“約束”でもあります。数字を定期的に見直す過程が、オンボーディングや人事施策の改善点を炙り出します。

3 まず何を出すか:最小セットの考え方
はじめから全指標を整備しようとすると続きません。最小セット → 補助情報 → 詳細の順で広げます。
・定着率の定義(例:入社〇年時点の在籍率)。分母・分子・対象期間を明記します。
・平均勤続年数(直近決算期の数値)。在籍者のみで計算か、退職者を含むかを注記します。
・育休取得・復帰に関する指標(取得者数/復職者数)。性別での分解は任意ですが、可能なら公開します。
・オンボーディングの枠組み(初月の伴走体制、メンター有無)。数字で語れない“仕組み”を添えます。
・更新タイミング(四半期または半期など)。次回更新予定日を一緒に載せます。
数字は単独で置かないのがコツです。必ず「対象範囲」「計算方法」「補足(特有の事情)」をセットにします。

4 “見せ方”の設計:誤解を生まないためのルール
分母を隠さない
「定着率〇%」だけでは解釈できません。母数と対象層(新卒・中途・職種)を記載します。
期間の並列表示
単年だけだと変動の影響が大きく見えます。直近3期を横並びにして傾向を見せます。
中央値(メディアン)も検討
平均だけだと一部の長期在籍が全体を引き上げます。可能なら中央値も併記します。
注釈は短く・具体的に
「繁忙期にプロジェクト増加で入れ替わりが生じた」など、事実を短文で添えます。言い訳に見えない粒度が重要です。
画像ではなくテキストも
グラフ画像だけだと検索に引っかかりません。テキスト(HTML)での併記を基本にします。

5 どこに置くか:候補者が本当に見る場所
・採用トップページの“数字の概要”:一画面で要点が分かる場所に。
・募集要項の直下:応募の判断に直接効く位置に補足します。
・選考案内メール:一次面接の案内文に、オンボーディングや定着支援の要点を一段落で。
・会社説明資料:体系立てて説明できるよう、社外公開版を用意します。
・入社後のハンドブック:公開内容と社内運用を一致させます。
“見せっぱなし”にならないよう、選考の接点すべてで同じ表現が出るように整えます。

6 言い回しの例:強がらない、誇張しない
・「直近3期の在籍状況をまとめました。対象と計算方法は下記の通りです。」
・「職種別の傾向があります。ご応募職種のデータは面談時に詳細をご案内します。」
・「数字は改善途上です。オンボーディングの見直し内容をあわせて公開します。」
・「家庭や進学など自己都合の退職も含みます。理由の内訳は年次レポートに記載しています。」
どの文も、余計な形容詞を足さず、事実→補足→約束の順に並べます。

7 公開の前に整える“定義表”
公開の一貫性は定義の統一から生まれます。以下のような一枚を作り、採用・人事・広報・現場で共有します。
・対象期間(決算期ベースか暦年か)
・対象者(正社員のみ/有期含む/新卒・中途の扱い)
・計算方法(在籍判定の基準日、出向・休職の扱い)
・指標の更新頻度と責任部門
・注釈のテンプレート(最大2行で簡潔に)
これがあるだけで、媒体ごとの表記ブレや“数字の使い回し”による齟齬を防げます。

8 透明化と同時にやるべき定着支援
定着率は結果です。公開と同時に、原因側の手当ても進めます。
仕事のサイズ合わせ:最初の3ヶ月は難易度の段差を小さくし、成功体験を積ませます。
・1on1の頻度と質の担保:回数だけでなく、話すテーマの事前共有を標準化します。
・メンター制度の“実効性”:名前だけのメンターにしない。評価に反映する仕組みを作ります。
・配属前の情報開示:チームの働き方や使用ツール、会議体を候補者にも説明できる状態にします。
“出す勇気”と“直す意志”はセットです。数字を出して終わりにしないことが、次の応募者への誠実さになります。

9 やってはいけない見せ方
分母のすり替え
試用期間を除いたり、特定の職種だけを抜いたりして見栄えを良くするのは禁物です。注釈で範囲を明示します。
単年の“良い年”だけを強調
波があるのは当然ですが、良い年だけを切り取ると信頼を失います。推移で見せる前提にします。
更新を止める
一度出した数字を更新しないのは逆効果です。予定日を宣言し、守れないときは理由を添えて延期を告知します。
PDFだけに閉じる
候補者はスマホで見ることが増えています。軽いページで、スクロールで要点が読めるようにします。

10 効果の見方:誇張しない定量・定性
定量
・一次辞退の理由に「情報不足」がどの程度減ったか
・面談設定までの往復回数の変化
・説明会・求人ページの滞在時間やスクロール完了率
定性
・面接での質問の質がどう変わったか(業務深掘りが増えるなど)
・入社後アンケートの「入社前情報の正確さ」への評価
・社内からの「数字公開が行動を変えた」声
派手な数字を掲げる必要はありません。摩擦が減ったかどうかを、現場の肌感と合わせて見るのが現実的です。

11 小さく始めるステップ
1. 対象と定義を決める(新卒・中途のどちらから始めるか、期間はどこからどこまでか)。
2. 採用サイトに“数字+注釈”を1ブロック追加。画像ではなくテキスト中心で。
3. 選考メールに一文を追記(「在籍状況の概要はこちら」)。
4. 月次で更新可否を確認。変更がなければ「変更なし」の明記だけでも十分です。
5. 候補者・現場からのフィードバックを回収し、項目を見直します。
完璧を目指すより、続けられる枠組みを先に作る方が効果が出ます。

12 候補者に“読み方”を渡す
数字は読み解きが必要です。ページの最後に短い“読み方ガイド”を置くと親切です。
・「部署や職種で傾向が異なります。面談で個別の実情をお伝えします。」
・「創業期は変動が大きいです。直近の取り組みと合わせて評価してください。」
・「平均と中央値の両方を載せています。分布の偏りもご確認ください。」
こちらから解釈の軸を渡すことで、数字が独り歩きするリスクを減らせます。

13 現場を巻き込む:説明できる“口癖”を揃える
候補者が信頼するのは、数字そのものより語る人です。面接官・現場リーダーが同じ言い回しで説明できるよう、短い“口癖”を揃えておきます。
・「定着は結果、仕組みは原因。私たちは原因側(オンボーディング)を毎期見直しています。」
・「数字は上振れ下振れがあります。傾向と、直近の手当てを一緒に見てください。」
・「合う・合わないがあるので、仕事の実態は包み隠さず説明します。」
人の言葉が、数字の信頼を支えます。

14 まとめ:完璧さより、更新され続ける“正直さ”
定着率を出せる企業は、候補者の時間と意思決定を尊重していると受け止められます。良い年もあれば、うまくいかない年もある。その揺らぎごと見せて、定義と注釈を添える。定着を支える仕組みの手当ても同時に公開する。これらの積み重ねが、誇張のない静かな採用力になります。
今日できるのは、たった一つのブロックを採用サイトに足すことです。
「対象・期間・計算方法・更新予定日」を明記したシンプルな数字。
それだけで、候補者の目線は変わります。隠さない姿勢は、派手ではありませんが、確実に選ばれる側の条件になります。
もし、この最初の一歩で迷われたり、自社に合った見せ方を知りたいと思われたりしましたら、いつでもお気軽にご相談ください。貴社ならではの誠実さが伝わるよう、私たちがしっかりとサポートいたします。