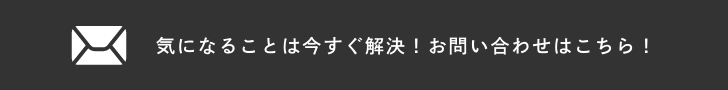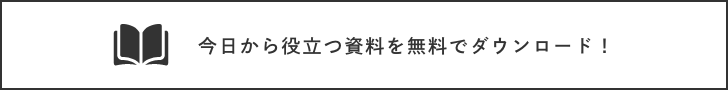INDEX
1 はじめに:読める文章は、それだけで“好意”を稼ぐ
内容が同じでも、読みやすい文章は最後まで読まれやすく、理解も早く、好印象が残ります。逆に、文字が小さい・詰まっている・行が長すぎる——このどれか一つでもあると、内容の良し悪しに関係なく「しんどい」と感じて離脱が増えます。
フォントや行間は、見た目の趣味ではありません。読む人の負担を減らすための設計です。大掛かりなリニューアルをしなくても、文字まわりを整えるだけで体験は十分に変わります。本稿では、日々の制作で迷いがちなポイントを“実務で使える基準”に落とし込み、等身大のコツとしてまとめました。
2 読みにくさの正体:5つの要因を押さえる
読みにくさは、たいてい複合要因です。まずは“何が重なっているのか”を分解して捉えましょう。
①フォントの性格
字形の癖、線の太さ、文字の詰まり具合。明朝体は横線が細く、小さい画面だと欠けやすい。一方、ゴシック体は線の太さが安定し、サイズを落としても崩れにくい。
②サイズと行長
文字が小さすぎる、または1行に詰め込みすぎると、視線の往復が増えて疲れます。
③行間と段落の余白
行と行、段落と段落の“空気”が足りないと、ベタッと見えて意味の塊が取り出しにくい。
④コントラスト
薄いグレー文字、淡い背景、細いウェイトの組み合わせは、環境光の下で一気に読みにくくなります。
⑤記号・数字・英字の扱い
全角・半角が混ざる、等幅とプロポーショナルが混在する——こうした“ちぐはぐ”がリズムを壊します。
この5点を見直すだけで、体感はぐっと変わります。細部をいじる前に、まずは大枠から整えるのが近道です。
3 フォント選び:まずは“素直で癖の少ないゴシック”から
長文の本文には向きません。見出し・キャプション・読み物ページのアクセントなど、サイズを確保できる場面で使うと品よく収まります。
明朝体は用途を絞る
長文の本文には向きません。見出し・キャプション・読み物ページのアクセントなど、サイズを確保できる場面で使うと品よく収まります。
ウェイトは中庸が基本
本文は極端に細い・太いを避け、標準〜やや太め(英語でいう Regular〜Medium 相当)に。細すぎるとコントラスト次第で消えます。
太字は“強調のためだけに”
1段落に太字が多いと、どこが重要なのか分からなくなります。太字のルールはひとつに決め、使いどころを節約しましょう。
フォントの数は絞る
本文用・見出し用・英数字用で最大2〜3種程度が目安。増えるほどリズムが乱れます。
英数字・数字の表情
価格や日時が多いページは、数字の読みやすさで選ぶと失敗が減ります。0とO、1とIの見分け、桁区切りの揃い方を確認しておきましょう。
丸ゴシックの扱い
やわらかい印象を出したい時に効果的ですが、長文では甘く見えがち。本文すべてではなく、アイキャッチや注記にポイント使いする方が扱いやすいです。
フォント選びは、ブランドらしさと可読性の折り合いです。迷ったら“素直なゴシックをベースに、見出しだけで変化をつける”から始めてください。

4 サイズ・行長・コントラスト:読みやすさの土台づくり
次に、視認性の土台を固めます。ここが整うと、行間の微調整が効いてきます。
サイズの目安
スマホ本文は「拡大しなくても読める」を基準に。小さく感じたら潔く上げる。見出しは本文の約1.4〜2倍を目安にし、段階を作ると情報の層が見えます。
行長の目安
スマホは全角で15〜25字程度、PCは40〜60字程度だと、視線の折り返しがスムーズな人が多いです。1行が極端に長くなるレイアウトは避けましょう。
左右の余白
本文左右に呼吸できる余白を。画面端ぎりぎりまで流すと、視線が窮屈になります。
コントラスト
淡いグレー文字×薄い背景は避け、黒に寄せた文字色×十分に明るい背景を基本に。リンクは色だけでなく下線や太さでも区別すると安心です。
背景の装飾
模様や写真の上に本文を載せるときは、一段かませる(薄い白板を敷く、不透明度を上げるなど)。読みやすさを最優先に考えます。
こうした“地味な調整”が、実は一番効きます。文字に目が行く前にストレスを生む要素を、先回りで取り除く発想です。
5 行間設定:数字を当てるのではなく“息継ぎ”を整える
行間(行送り)は、読む速度と理解度に直結します。詰まりすぎると息苦しく、空けすぎると行がバラけて、意味の塊が崩れます。コツは文の長さと行長に合わせて微調整すること。
短文×短い行長
行間は控えめに。文字と文字の連続性が保たれ、テンポよく読めます。
長文×長い行長
行間をやや広げ、視線の戻りを助けます。段落間の余白も気持ち多めに取ると、次のかたまりへ移りやすい。
見出しと本文の距離
見出しの下に余白を作る(上を詰め、下を広げる)と、見出しが“次の本文のラベル”として機能します。
箇条書きの行間
各項目はやや詰め、項目間にだけ余白を置くとリズムが整います。
全角記号の跳ね返り
句読点や括弧の直後に“妙な空き”が出る場合は、該当の文字の前後だけ詰める意識で。読み流しのつっかえを取るイメージです。
行間は「数字を決めて終わり」ではなく、本文の表情を見ながら決めるのが肝心です。仕上がりを声に出して読んでみると、詰まりや間延びに気づきやすくなります。
6 段落・強調・記号:読みやすさを壊さない“装飾の作法”
読みやすさは、装飾の“やりすぎ”で簡単に壊れます。役割を決めて、必要最低限にしましょう。
段落頭
行頭一字下げか、下げなし+段落間マージンか、どちらかに統一。併用すると混乱のもとです。Webでは段落間マージン方式が扱いやすい場面が多い。
強調の優先順位
太字>色>下線の順に使うと整理しやすい。リンクは色と下線、本文の強調は太字——と役割を分けると衝突しません。
全角・半角の混在
数字や記号は用途に応じて統一(例:日付・価格は半角、文章中の補助は全角、など)。揃っているだけで読み口が滑らかになります。
カギ括弧と引用
会話や借用は「」や――だけに頼らず、引用ブロックや字下げで視覚的にも区別する。
見出しの段差
H2・H3・H4…を使うなら、サイズ・太さ・余白の“段差”をしっかり付ける。変化が小さいと、どこが階層なのか分かりません。
絵文字・顔文字
親近感は出ますが、長文では視線を散らします。案内文や注意書きでは控えめに。
“装飾=親切”ではありません。ルールを減らして、例外を作らないほうが、結果として読みやすくなります。

7 仕上げと運用:画面と環境を変えて最終チェック
文字周りは一度整えて終わりではありません。読む環境で印象が変わるからです。最後は実機で、複数の状況を想定して確認します。
距離を変える
デスクでの閲覧と、通勤電車での片手操作では見え方が違います。スマホは片手で親指スクロールしながら、引っかかる行を探す。
明るさを変える
日差しの下・暗い室内で、コントラストが足りているかを確認。薄いグレーはすぐに読みづらくなります。
長文テスト
見出し〜本文〜箇条書き〜注記の一連を続けて読み、テンポが崩れる箇所を探す。段落間の余白を1〜2段階動かすだけで解消することが多いです。
更新時の“事故防止”
制作チームや外部ライターがいる場合は、フォント・サイズ・行間・見出し階層の簡易ルールを1枚にまとめ、共通の“物差し”を持つ。
運用でぶれさせないことが、読みやすさを保つ一番の近道です。ルールは短く、守れる数に絞りましょう。
8 まとめ:読みやすさは“気配りの連続”で決まる
読みやすい文章は、特別なテクニックではなく、小さな気配りの積み重ねです。
1)癖の少ないゴシックを軸に、フォント数は絞る。
2)サイズ・行長・コントラストで“土台”を作る。
3)行間は本文の長さと行長に合わせて整える。
4)段落・強調・記号は役割を決めて最小限に。
5)実機・実環境で確認し、運用ルールを短く共有する。
この順番で見直すだけで、読む負担は目に見えて下がります。大げさな改修より、今日いじれるところから。まずは本文サイズを一段上げ、行間と段落の余白を少しだけ広げる。それだけでも、読み終わる人は確実に増えます。読者にとっての“読みやすさ”は、一番手前の体験。ここが整っていれば、内容の良さは自然と伝わります。
また、当社ではウェブサイトの読みやすさ改善に関するサポートも提供しております。フォント選びや行間設定など、デザインのことでお困りの点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。専門のスタッフが、お客様一人ひとりの状況に合わせて丁寧に対応いたします。ご相談を心よりお待ちしております。