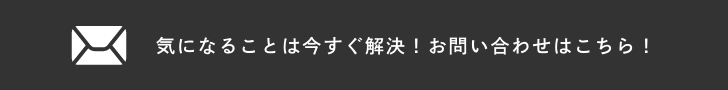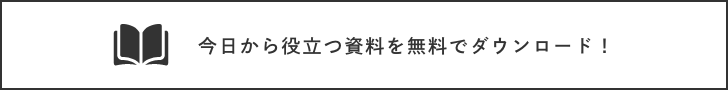INDEX
1 はじめに:同じ会社でも読者の期待はまったく違う
企業ブログという言葉が広まり、情報発信のハードルは劇的に下がりました。しかし実際の運用現場では「製品アップデートの記事と社員インタビューが同じフィードに並び、どちらも読まれにくい」という悩みが絶えません。理由は単純で、コーポレートの読者(顧客・パートナー・メディア) が欲しい情報と、採用候補者 が知りたい情報は根本的に異なるからです。片方の期待に沿って記事を作るたび、もう片方の読者は離脱し、アルゴリズムもテーマが揺れるメディアを評価しにくくなる――これが「何を書いても数字が伸びない」状態の正体です。

2 分ける? 一体運用? 判断基準はたった二つ
ブログを完全に分離するか、一つのドメイン内でカテゴリ分けするか。迷ったときは次の二つだけを指針にしてください。
1. 読者の検索意図が重なっているか
もし「製品名+使い方」で流入したユーザーが、人事制度の記事も読みたくなる可能性が低いなら、検索体験を分けた方が親切です。一方でスタートアップのように製品とカルチャーが強く連動する場合は共存も選択肢になります。
2. 運用リソースを二本立てで維持できるか
別ドメイン・別CMSにすると更新フローも解析も二重になります。編集会議や計測ダッシュボードを整理し、「分けた途端に片方が止まる」リスクを許容できるかが現実的な判断軸です。

3 もし分けるなら──それぞれの“使命”を掘り下げる
3‑1 コーポレートブログ:信頼と専門性を積み上げる場
ここでは製品アップデート、導入事例、業界トレンド解説など、顧客の購買判断を後押しする情報 に絞ることが重要です。記事構成は「課題 → 解決策 → 当社の提供価値」という王道フォーマットで統一し、最後に必ず CTA(資料DLやデモ申込)を置きます。執筆者の肩書きは“プロダクトマネージャー”“テックリード”など権威性のある役割を明記し、専門ブログとしての格を保ちましょう。
3‑2 採用ブログ:カルチャーを可視化し共感を誘う場
読者は「ここで働く自分」を想像したいだけで、製品仕様には興味がありません。インタビューや1日のタイムライン、評価制度の舞台裏など、日常の温度が伝わるコンテンツ を中心に据えます。CTA は求人一覧だけでなく、「カジュアル面談申込み」や「社内イベントの公開録画」などハードルを複数用意すると、母数の広い候補者が次の一歩を踏みやすくなります。

4 一体運用を選ぶなら──情報の“住み分け”をUIで解決
ドメインを分けない場合も、トップページをスクロールすると営業記事と採用記事がランダムに現れる状態は避けたいところです。タグやカテゴリで分けるだけでなく、ファーストビューに二つの入口バナーを常設 し、クリックした瞬間に別レイヤーの一覧へ遷移させる方法が有効です。URL 構造も /blog/business/ と /blog/culture/ に切り分け、Google のサイトリンク表示で読み分けられるようにしておくと SEO 的な評価も迷いません。

5 “両輪”で走らせるための編集カレンダーの作り方
片方の記事が続くともう一方が埋もれる現象を防ぐため、月間ロードマップを色分け して俯瞰できるカレンダーを作ります。例えば「火曜=コーポレート」「木曜=採用」と曜日で固定すれば、ネタ出しも運用もリズムが整います。さらに四半期ごとに「注力キーワード」と「注力ポジション」を並べ、検索流入と応募数を同時に追う KPI ダッシュボード を置くと、片方の数字だけが伸び悩んだ際に即座に手当てが可能です。

6 コンテンツ品質を保つ3つのコツ
1 “誰のセリフなのか” を消さない
専門記事ではエンジニアの語り口、カルチャー記事では新卒社員の戸惑いなど、人格込みで情報が届きます。編集段階で文体を均質化しすぎると体温が消え、読者はファクトしか受け取れません。
2 一貫コピーでブランドを橋渡しする
ページ最上部に置くタグラインやフッターのミッション文は両ブログで完全に一致させ、企業の根幹価値は揺らがないことを示します。
3 写真とアイキャッチのテイストを固定
カメラマンとレタッチのガイドを作り、色温度やトリミング規定を統一すると、フィードが雑誌のように読みやすくなり戻り読みが増えます。

7 測定なくして戦略なし──KPI は別建てで追う
同じ Google Analytics ダッシュボードに二種類の意図を混ぜ込むと、数字の意味づけが曖昧になります。推奨は ビューまたはプロパティを分ける方法。コーポレート側は「Organic 流入/資料DL/商談化率」、採用側は「SNS 流入/平均滞在時間/応募完了率」を主要指標に据え、四半期ごとに「読了率」や「シェア数」をサブ指標として分析します。こうして両輪で走りつつ、ゴール地点は別々に設定するのが最もブレない運用です。
8 おわりに:分けるか、繋げるかは“目的の純度”が決める
コーポレートと採用のブログをどう設計すべきか――答えは組織の規模やリソースではなく、「それぞれの読者に何を感じてほしいか」という目的の純度で決まります。もし両方の読者が同じ記事を読んで価値を感じるのなら一体運用でも問題ありません。しかし多くのケースでは、顧客は課題解決の実績を、候補者は働く人の物語を求めています。
目的に合わせて体験を整えることが、結局はコンテンツの力を最大化する近道。まずは自社のブログを読み返し、「この情報は誰に向けているのか」を一つひとつ問い直してみてください。タグの整理、カテゴリの分割、もしくはドメインの分離――次の一手が自然に見えてくるはずです。
今回ご紹介したポイントを参考に、自社のコンテンツ戦略をぜひ見直してみてください。もし「どちらの設計が最適か判断が難しい」「運用にリソースを割けるか不安」といった課題があれば、当社のサポートをご活用いただけます。経験豊富なスタッフが、あなたのビジネスに最適なアプローチをご提案いたします。