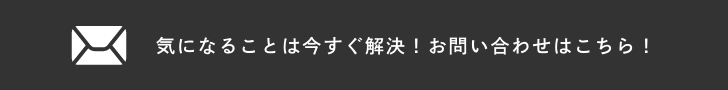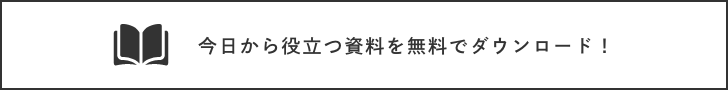INDEX
1 はじめに:指標は「体温計」、変化と組み合わせで読む
アクセス解析ツールを開くと、PV数やセッション数と並んで必ず表示される「直帰率」と「滞在時間」。これらの数字を見て、「直帰率が高いからダメだ」「滞在時間が短いから読まれていない」と、短絡的に判断してはいないでしょうか?
これらの指標は、単体で見るのではなく「組み合わせて」見ること、そして「ページの種類」によって基準を変えることで、初めて意味を持ちます。
この記事では、サイト改善のヒントを見つけるために、直帰率と滞在時間という2つの指標をどう読み解き、具体的なアクションに繋げるか、その実践的な方法を解説します。
2 「直帰率」と「滞在時間」の基本
直帰率 (Bounce Rate)
サイトに訪問したユーザーが、最初の1ページだけを見て、他のページに移動せずにサイトから離脱した割合のことです。サイト全体の“入口の体温”を測るような指標です。
滞在時間 (Average Time on Page)
ユーザーが特定のページを閲覧していた時間の平均値です。ユーザーがそのコンテンツにどれだけ集中していたか、興味を持っていたかを示す指標となります。

3 GA4では「エンゲージメント率」が主流に
最新のGoogle アナリティクス 4(GA4)では、「直帰率」はデフォルトで表示されなくなりました(※設定で表示は可能)。代わりに「エンゲージメント率」という指標がメインになっています。
これは、「10秒以上滞在した」「2ページ以上見た」「コンバージョンした」のいずれかを満たしたセッションの割合を示すもので、「直帰=悪」と捉えるのではなく、「どれだけ意味のある訪問だったか」を重視する考え方です。とはいえ、「1ページだけ見て離脱した」という事実は依然として重要ですので、本記事では、この「直帰」という現象をどう改善するかという視点で話を進めます。
4 分析の前に:「良い直帰率」はページの種類で変わる
最も重要な前提として、「理想の直帰率」はページの目的によって全く異なります。
直帰率が高くてもOKなページ
ブログ記事・FAQ:検索で訪れたユーザーが、その記事だけで疑問を解決し、満足して離脱するケースが多いため。
会社概要・アクセスページ:住所や電話番号だけを確認して閉じるのが目的なので、直帰しても問題ありません。
直帰率が低いことが理想のページ
トップページ:サイトの「玄関」であり、ここから各ページへ回遊してもらう必要があるため。
ランディングページ(LP):最終的なコンバージョン(購入・問い合わせ)へ誘導するのが目的なので、途中で離脱されるのは問題です。
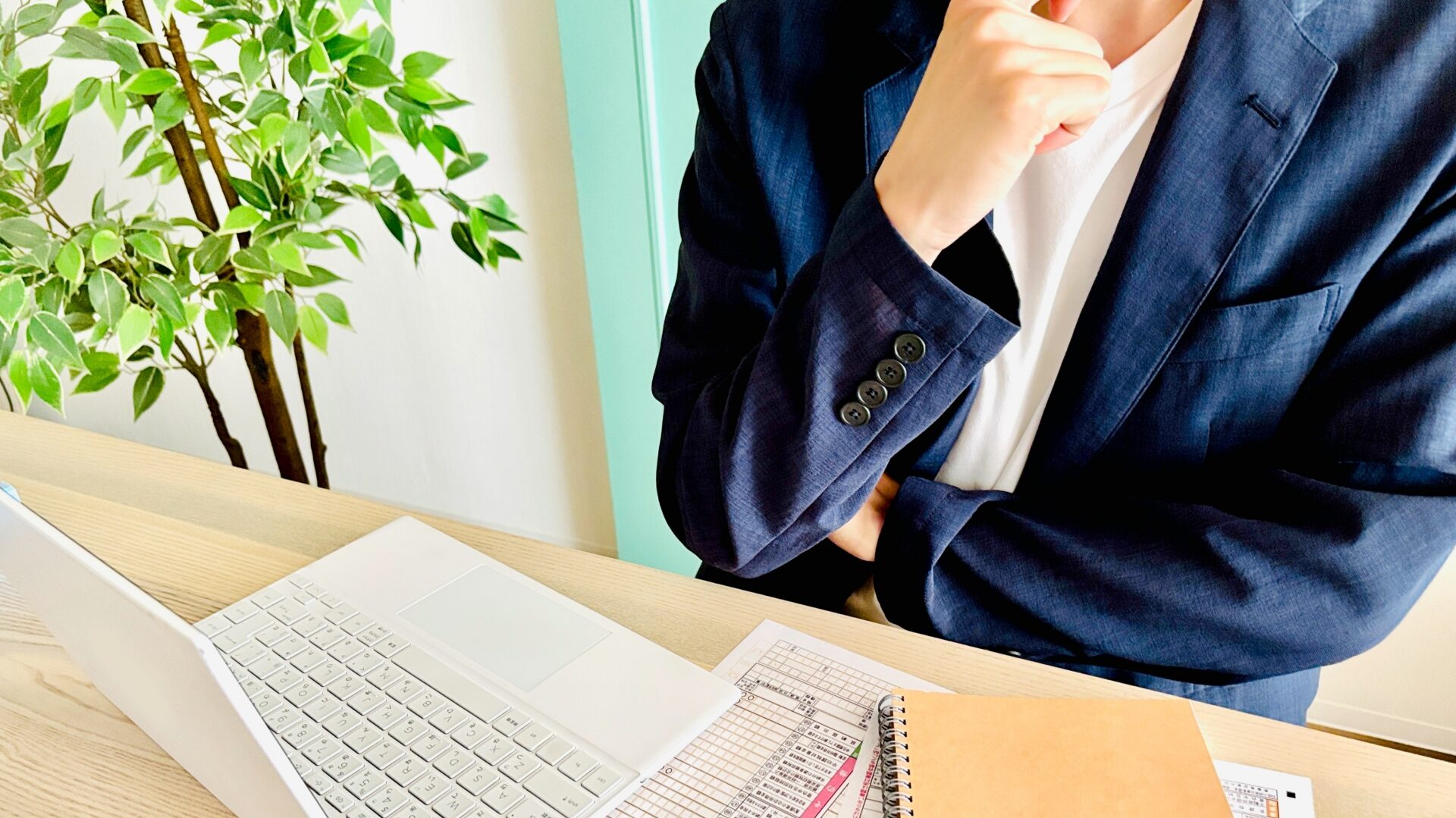
5 象限で分析する「直帰率 × 滞在時間」
分析すべきページ(トップページやLPなど)を特定したら、この2つの指標を掛け合わせて分析します。
象限A:直帰【高】 × 滞在【短】 = 最も危険な状態
仮説:訪問者が「求めていた情報と違う」と瞬時に判断し、離脱しています。
対策:広告文や検索キーワードと、ページのファーストビュー(最初に表示される画面)の内容が一致しているか、根本的に見直す必要があります。
象限B:直帰【低】 × 滞在【短】 = 回遊しているが、読んでいない
仮説:ページは次々見ているが、一つひとつのコンテンツは読み飛ばされています。サイトのデザインやナビゲーションに興味はあるが、中身が響いていない可能性があります。
対策:各ページのタイトルや見出しを、よりユーザーの興味を引くものに改善できないか検討します。
象限C:直帰【低】 × 滞在【長】 = 理想的な状態
仮説:ページをしっかり読み込み、さらに興味を持って他のページへも移動しています。
対策:このページの何がユーザーを惹きつけ、次の行動を促したのか(例:記事の質、内部リンクの位置)を分析し、他のページにも横展開します。
象限D:直帰【高】 × 滞在【長】 = 満足したが、次の行動がない
仮説:コンテンツはしっかり読まれ、満足度は高い(例:ブログ記事)。しかし、1ページで完結してしまい、サイト内での次の行動(関連記事や資料請求)に繋がっていません。
対策:コンテンツの最後に、関連性の高い内部リンクや、CTA(行動喚起)を設置することで、回遊率やCVRを改善できる可能性が非常に高いです。
6 直帰率を下げる“入口”の手当て
直帰率が高いページ(特に象限A)は、「入口」の設計を見直します。
ファーストビューと検索意図の一致
ユーザーが検索したキーワードや、クリックした広告文から期待する「答え」が、ページを開いた瞬間に目に入る場所に提示されているかを確認します。
内部リンクの“導線設計”
ユーザーが次に何をすべきか迷わないよう、関連する情報への導線を分かりやすく設計します。記事の最後だけでなく、文中の適切な箇所にも内部リンクを設置します。
CTA(行動喚起)の最適化
「資料請求はこちら」「お問い合わせ」といったボタンが、目立つ色で、適切な位置に配置されているかを見直します。「今すぐ無料相談」のように、具体的な言葉(マイクロコピー)を工夫するだけでもクリック率は変わります。
7 滞在時間を伸ばす“読みやすさ”の設計
滞在時間が短いページ(特に象限B)は、「読みやすさ」を改善します。
結論ファーストとPREP法
ビジネス文書と同じく、Webコンテンツも「結論」から書き始めます。その上で、「Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論)」のPREP法で構成すると、論理的で読みやすい文章になります。
視覚的なリズム
スマートフォンの画面は、文字の塊が続くだけで読む気が失せます。適度な改行、箇条書き、太字での強調はもちろん、文字の塊を、2スクロールに1回程度は画像や図解といった視覚要素で区切ることで、読み進めるリズムが生まれます。
表示速度の改善
根本的な問題として、ページの表示速度が遅いと、コンテンツが読み込まれる前にユーザーは離脱します。画像のサイズを圧縮するなど、基本的な表示速度対策は必ず行いましょう。
8 おわりに:数字の“変化”から仮説を立てる
アクセス解析の数字は、あくまで結果です。大切なのは、その数字を見て「なぜそうなったのか?」という仮説を立て、改善のアクションを起こし、その後の「数字の変化」を見ることです。
直帰率と滞在時間という2つの「体温計」を正しく読み解き、サイトの健康状態を改善するヒントを見つけ出しましょう。
当社では、こうしたアクセス解析のデータに基づいた現状分析から、直帰率や滞在時間を改善するための具体的な施策立案・実行まで、一貫してサポートしております。「なんとなく」ではない、データに基づいたサイト改善をお手伝いいたします。
もし「自社サイトの数字、どう読めばいいか分からない」「改善したいけど、何から手をつければ…」とお悩みでしたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。御社の状況に合わせた最適なプランをご提案させていただきます。、「記事のこの部分について、もう少し詳しく聞きたい」といった小さなご質問だけでも大歓迎です。経験豊富なスタッフがしっかりとサポートいたしますので、どうぞご安心してお問い合わせください!